

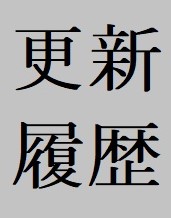
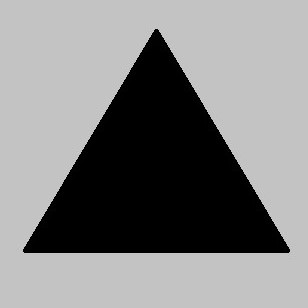

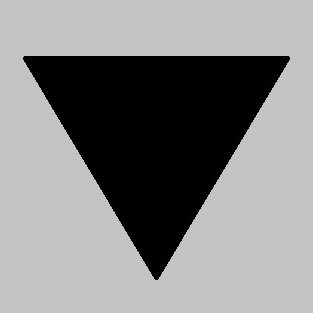

HOME>庄内加藤家
↑

|
| 忠広の室と子については前述しましたが、嫡子光正は忠広と同時に飛騨に配流され、その翌年に亡くなっています。 また沼田に預けられた、側室法乗院との子供である正良も、忠広が病没してから約一カ月後に亡くなっています。 忠広の預り人である酒井忠勝への幕府からの覚書には、忠広は子供を作ってはならない事、万一出来た場合には殺すようにと書かれていました。 忠広と正良の死を以て、文字通り加藤家は断絶となりました。清正からの血筋は、忠広の妹のあま姫から紀伊徳川家へと繋がるのみとなりました。 |
| 清浄院 家康の従兄妹 |
|||||||||
| 本覚院 菊池武宗の娘 | 清正 | 正応院 玉目丹波守の娘 | |||||||
| 忠正 | 古屋 | あま | 忠広 | ||||||
| 九歳で早世 | 榊原家、後に 阿部家に嫁す |
紀伊家初代 頼宣夫人 | 寛永九年改易 庄内丸岡へ | ||||||
| 清正の室と子 | |||||||||
| 玉目丹波守 (二代目) | ||||||||||||||||
| 蒲生秀行 (氏郷嫡男) | 振姫 (家康三女) | |||||||||||||||
| 女 丸岡での室 | 女 (忠広養女) | |||||||||||||||
| 法乗院 沼田へ | 忠広 | 宗法院 (秀忠養女) | ||||||||||||||
| 女 赦され江戸へ |
正良 沼田へ | 光正 飛騨へ配流 | ||||||||||||||
| 女 | 男 | |||||||||||||||
| 大山富三郎家 | 新堀勘右衛門家 | |||||||||||||||
忠広の室と子 | ||||||||||||||||
| しかし、正室宗法院と側室法乗院の他に、実は忠広にはもう一人側室がいました。この女性は、二代目玉目丹波守の三女で、法乗院の妹になります。 配所の丸岡には宗法院も法乗院も行っていませんが、このもう一人の側室が丸岡に同行し、配所での室となります。 そして忠広との間に男女二人の子供ができます。幕府の追求をのがれるため、天沢寺に二人の架空の墓を建て、 この子供達は密かに丸岡を抜け出しました。 |

天沢寺にある二人の墓碑 右:男子 円通院日達霊 左:女子 真如院妙善霊 (秋野庸太郎編「栄光冨士」より) |
| この男女二人が、後の新堀加藤家と大山加藤家に繋がっていきます。 |

新堀 勘右衛門家 |
| 男子(清十郎亀方あるいは熊太郎)は、現東田川郡三川町の加藤村で育てられ、後に光秋と名乗りました。 その子供の道久の時代に新堀に移り住み、勘右衛門家の始祖となりましたが、 その経緯を父は次のように書いています。 |
|
この兄の方の後裔は、現酒田市新堀の加藤一族で、総本家は勘右衛門と呼ばれている。同家には、忠広の遺品、古文書、系図等が伝えられているが、 それによると、次のような結論が導き出される。 即ち、忠広と奥方との間に生れた男子は、長じて丸岡配所を脱出し、現東田川郡三川村横山の一部落に隠れた。この部落は、そうした因縁によって、 其後加藤村と呼ばれている。この男子は光秋と云い、道久という男子一人があった。道久は、勿論加藤村に生れたわけだが、貞享年中新堀に移転し、 後藤又三郎と云う豪家の邸宅を買って居住した。勘右衛門家の系図も過去帳も、この道久から始まって居り、光秋、忠広、清正は、 先祖の父、祖父、曽祖父として記入されている。 “筆余附録”には、光秋が主計という名になっているが、横山の加藤村に脱出し、後新堀に移り、勘右衛門の祖になった事は同じである。 ただ、加藤村から一時狩川通主計新田(現東田川郡立川町)にとどまり、更に新堀(原文は新井堀)に移ったと云うことと、 勘右衛門の祖になったのは、忠広の孫に当る道久ではなく、丸岡を脱出した男子の主計(光秋)自身である点が、異なっている。 ところで、「清正公伝調査委員」の考証によれば、忠広の配所での奥方を、清十郎亀方の生母と呼んでいるし、 沼田関係(法乗院と正良)の古文書にも清十郎の名が見える。この奥方には、他に男子があった形跡は全くないので、 この清十郎亀方、光秋(主計)は同一人物ではないか。清十郎亀方というのは、丸岡館を脱出するまでの幼名で、 其後光秋(或は主計)と改めたとの推理も成立しそうだ。ちなみに、この男子は、忠広配流後の生誕と云われているが、沼田に配された側室や、 その子正良に関する古文書を見ると、清十郎亀方は、配流前すでに生誕していた公算が大である。沼田の側室は、 清十郎の生母の姉(二代目玉目丹波守長女)であり、肥後時代より共に側室であったのだから、清十郎が配流前の生誕であっても、 何等不自然ではない。天沢寺にある架空の墓に刻まれた「寛永十九年壬午三月」と云うのは、脱出の時期を示すものではないか。 伝説の一つに次のようなのがある。酒井が、忠広を慰める為に、三人の美女を侍女として配所へ送ったところ、横山の加藤村出身の一女が懐妊し、 里へ帰って男子を生んだ。この男子は熊太郎と呼ばれていたが、幼くして疫病で亡くなったと云う。又一説には、忠広が、子供の将来を考え、 自らの手で葬ったのだと云う。この伝説は、裏付けとなるようなものが皆無で、史実としては問題にならぬが、話はいろんな含みを持っていて、 なかなか興味深い。伝説にあるような事実はあるまいが、この部落出身の女が、丸岡館に奉公していたのではないか。その女が手引きして、 自分の里に、この悲劇を背負うた名門の若君を脱出させた。或いは、己の子供として連れ帰ったとしても、変ではない。 この男子が早世したことになっているのは、丸岡の墓と共に、将来幕府の追求をのがれる為には必要な手段であったろう。 忠広が、自らの手で葬ったというようなことは、丸岡を脱出させなければならない客観状勢と忠広の心境を、それとなく物語っているようだ。 |
|
(片山丈士「身は明星に似て 附記」より) |
|
この家は、代々荒れ地を耕しては田畑を増やし、庄内きっての豪農となっていきました。決して素性を明かすことはなく、“加藤”も名乗りませんでした。
忠広からの繋がりについては、代々当主から当主へ口伝えで伝えられてきたそうです。架空の墓まで建てて幕府を欺いたわけで、
その素性がはっきり分かる資料など存在するわけはありませんが、唯一、道久からの系図が残っていました。その系図は裏が袋状になっていて、
開けると、上述のように“清正(曾祖父)−忠広(祖父)−光秋(父)”と記載されていたそうです。 庄内藩主の酒井家は、この勘右衛門家の存在を知っていました。明治天皇の東北行幸で庄内に休処を探す際に、 酒井家はこの勘右衛門家を紹介したそうです。最後まで官軍に抵抗した庄内藩主としては、 酒井家に関係した屋敷を提供するわけにはいかないということだったようです。宮内省がこの勘右衛門家を調査し、 明治天皇が立ち寄ることになりました。長く歴史の裏側で息をひそめていたこの家が、初めて表舞台に登場することとなりました。 この時家の者は蔵の中に閉じ込められ、外には出られなかったそうですが、しかし父の祖母が唯一人、 明治天皇の接待係をしたという話を父から聞いています。現在、庭に聖蹟碑が立っています。 |

勘右衛門家の明治天皇聖蹟碑 |
|
この百姓勘右衛門の家は、江戸時代、豪農とは言え決して表舞台に出ることはありませんでしたが、
しかし実は庄内藩にとっては大きな功績がありました。それは、日本一の大地主と言われ、
庄内藩の財政を支えた酒田本間家との関係です。道久から数えて三代目の了然の長女於世根が、
酒田本間家二代の光寿に嫁ぎ、その長男が本間家中興の祖と言われている三代光丘です。また、
勘右衛門家四代主膳の長女美屋は、光寿の末の弟で光丘の叔父に当たる古作(後の宗久)に嫁いでいます。 本間宗久についてはここで詳述する必要はないかと思いますが、米相場で莫大な財を築き、江戸根岸に邸宅を構え、 江戸本間家(根岸本間家)の始祖となった人です。現代でも相場の神様と呼ばれています。幕府の財政指南役もつとめていました。 この宗久と美屋とのあいだに子供は出来たのですが、早世したため、 美屋の弟にあたる四代主膳の五男猪四郎を養子に迎え、後を継がせています。(勘右衛門家の系図に記載されている) ちなみに、この後の話もあります。幕末に、江戸本間家は庄内に逃げ帰るのですが、この時に、酒田本間家ではなく、 二代猪四郎の実家である新堀の勘右衛門家を頼っています。維新後に勘右衛門家本家の近くに分家し、 本間古作家と呼ばれていたようです。勘右衛門家九代の孝治郎の四女菊江がこの家に嫁いでいます。 父の祖母豊は九代孝治郎の妹ですが、一時期江戸本間家の人達と暮らしていたと思われます。 豊は死の床で父に、江戸本間家の人達が庄内へ逃げ帰るとき、家の財を官軍の手に渡らぬよう、 ある場所に隠してきたという話をしたそうです。もちろんこの話の真偽はわかりません。 それから勘右衛門家には、忠広死後に用済みになった家臣によって、清十郎(もしくは熊太郎)のもとへ、 清正ゆかりの品として届けられた毘沙門尊天像が残っています。この時、妹の方には清正愛用の手槍の柄が届けられました。 |

勘右衛門家に伝わる毘沙門尊天像 (佐藤義久”庄内に於ける 加藤清正の孫と形見”より) |

大山 冨士酒造 |
| この家は古くから忠広に繋がる家柄であるとの伝承があり、開元としてまた先祖の母として女子(転誉妙延大姉)が特別な扱いを受けてきました。 |
|
妹の後は、明らかに、現西田川郡大山町の加藤家と思われる。「思われる」と書いたのは、決め手となるようなものが発見されないからであるが、 「明らかに」と書いた通り、推定では殆ど間違いなさそうだ。理由はいろいろあるが、二、三興味ある事実を書くにとどめる。 大山加藤一族の総本家は、冨三郎家であるが、同家及び、明治初年に分家した専十郎家の過去帳に、加藤家開祖として轉譽妙延大姉なる女子の名が記されている。 享保四亥正月、行年八十九才とある。この女子の墓は、加藤家の菩提寺である同町専念寺にあり、開元という字と、過去帳にある戒名や年月日が、 おぼろげながら読解出来る。冨三郎家の現当主の談によれば、この墓石は当時のままであると云う。 現冨三郎氏(昭和30年当時)の実兄に当る専十郎氏の談によれば、この女子は加藤治右エ門家に嫁し、子供(男子)を連れ同家を出、 冨三郎家を創立したものと云う。この男子は、治右エ門の子ではなく、連子であると云う伝説もあるらしい。この治右エ門家も現存している。 ともかく、あの男尊女卑の時代に、夫や息子が陰に引込んで、この女子のみが開祖とか開元とか別格の扱いを受けているのには、 勿論それだけの理由がなければならない。これは決してありきたりの事ではないのである。 この女子は、享保四年に八十九才で亡くなったとあるから、寛永八年に生れた事になる。しかし、命日の享保四年は、過去帳も墓石も一致しているので問題はあるまいが、 過去帳にある行年八十九才というのは、必ずしも信ずるに足らない。この時代の人の年令には誤りが多く、この女子のように、 複雑な生涯を送った長命な人の場合は、特に甚だしいとも思えるからだ。がしかし、これ以外に年令を知る手がかりがないので、 確かなことは何も云えない。 寛永八年と云えば忠広配流の前年に当たる。が、この年令が正しく、この女子が配流前の生誕であっても、一笑に附するわけには行かぬものがあるのだ。 と云うのは、兄の場合と同じように、沼田関係の古文書の中に、この女子の生前の名とおぼしきものがみえるからだ。 それは、沼田の側室とその子正良が、兄清十郎に宛てた書簡である。天沢寺の架空の墓に刻まれた「正保四年・・・」は、兄と同じように、 この女子が丸岡を脱出した時を示しているのではないか。数え年で十七才になるわけだ。 時代も年格好も客観的な状況も、この女子が忠広の娘(清十郎の妹)であるとして、何一つ不自然なものがないのは、極めて面白い。 冨三郎家には、清正愛用の槍の柄なるものが残っている。これは、一尺位の螺鈿の柄の一部に過ぎないが、私は直に、“校合雑記”の一文を思い出した。 忠広が、池上本門寺で配流の申渡しを受けた後、清正愛用の槍を取り出し、使者の前でたたき折ったと云う一文がある。 家来達が、その折れた槍の柄を、家宝として分け合ったと書いてある。富三郎家の槍の柄の一部が、その槍に当たるかどうかは、勿論わからないが、 ともかく興味ある事柄には違いない。 専十郎氏の談によれば、加藤家は、最初一農家としてひっそりと生活していたが、三代目頃から酒造りを始めたらしい。現在、 総本家の冨三郎家及び分家の嘉八郎家等は名だたる酒造家である。 |
|
(片山丈士「身は明星に似て 附記」より) |
|
しかし近年、分家の土蔵の扉の陰に保存されていた系図が発見され、その内容からもこの女子が忠広の娘であるとされています。
この女子は七才で大山の加藤治右エ門家に密かに落ちのび、後に治右エ門家から冨三郎家として正式に分家したそうです。その後、
1778年に酒造業を創業し、現在の冨士酒造に至っています。 平成25年の夏にこの冨士酒造を訪ねました。 |

|

|
| この家に伝わる、清正愛用の槍の柄を見せていただきました。 |

|

冨三郎家に伝わる清正の手槍柄 |
|
箱書きには、 “ 加藤肥後守清正公・・・ 淨池院殿永運日乗大居士 大神祇 六月廿四日 “ とありました。淨池院殿永運日乗大居士というのは清正の戒名で、6月24日は命日です。 横には“御手槍柄”と書かれていました。槍の柄は螺鈿細工が施されていて、いたるところに傷がありました。 勘右衛門家の毘沙門尊天像と同様に、忠広没後に家臣によって届けられたようですが、 この手槍柄と毘沙門尊天像、三百数十年の時を経て、近く再会の時がこないものかと期待しています。 |
|
● ● ● ●
|
| 最後に、父の子供の頃の話や、加藤家の人々の事、また忠広について調査を始めるきっかけとなった事などについてまとめた、 「身は明星に似て」附記の中の”雑録”と題された文章を紹介します。ちょっと長いですが、全文を掲載します。 |
|
(一) |
|
私の故郷、現酒田市新堀は庄内平野のほぼ中央に位置している。最上川が、広い川原をともなって側を流れ、対岸には、
出羽富士の鳥海山が秀麗な姿を現しているが、海にも山にもほど遠い何の変哲もない純農村だ。 戦前(現在は荒れ果ててしまったが)、三百戸に近い村の西北に、忠広の子孫といわれる加藤勘右衛門の屋敷が、 古めかしい外容を誇っていた。一万坪余の庭園と広大な家屋は、古い松林に囲まれ、その外側は更にひばの垣をのせた高い築地になっていて、 小さな小川が周囲を流れている。この家が、私の生家の本家である。私の家は、祖母が医師であった祖父を聟に迎え、 本家の直ぐ側に医院を建てて別れた。亡父も祖父の業を継いだが、不肖の子である私が嫌ったので、医業は二代にして終わってしまった。 私が子供の頃、大掃除の折、高い踏台に上って、上の神棚を片づけている下男の後から、恐る恐る覗き込んだことがある。 私の家は神道だったので(本家もそうであった)、分家してからの故人を祭るのは下、遠い祖先や、いわゆる神様を祭るのが上と、 二つの神棚があり、上には高い天井の直ぐ下にあって、いつもは幕がチラリと見えるだけであった。その時、私は奥の方に妙に光るものを見つけ、 下男からそれを前の方に引張って貰うと、衣冠束帯を着け笏を持った一尺位の木製の座像で、光るものはその眼であった。 祖母に聞いたら清正の像であると云う。私にはその眼が何故光るのか甚だ不思議でならず、人気のない折、踏台を持出して覗き込んだことがあるが、 何か恐しくて、像を取出すことが出来なかった。其後弟妹達に、“こわいものを見せてやるぞ”と、踏台にのせて覗き込ませ、 “そらそら光る光る”と云っては、みんなでわぁっと逃げたりしたのを覚えている。 戦後帰郷し、近くの市に住むようになってから、忠広の遺蹟を調べている人と話合った時、ふとそのことを想い出し、話したら、 その人は眼を丸くして、それは今何処にあると云う。探せば何処からか出て来るだろうと答えたら、是非探してくれと云うことであった。 何でも清正の像には二つの優れたものがあって、一つは鎧甲、一つは衣冠束帯なのだが、武装のは丸岡村で発見され、 その眼も光っていると云う。 早速故郷の妹に問い合せて調べて貰ったのだが、皆目わからないと云う。私が帰郷の意志がない上に、弟妹達もそれぞれ在京の上級学校へ進んでいたので、 一人残った母も、一時上京したことがあった。その際どっかへ片づけたものらしい。しかし妹は、キラキラ光る眼のことを覚えていた。 私の家には其他に、甲冑、槍、刀があった。本家もそうであったが、私の家なども常に新しいものを追いかけているような雰囲気だったので、 そんな古いものに興味を覚えたり、大切にしたりするものもなく、甚だ粗末に取り扱われていた。 甲冑は櫃にはいったまま蔵の中にあったが、毎年あちこちの祭礼に貸してやったり、私達がよく引っ張り出してはいたずらをしていた。 槍は一室の長押しにかかったまま忘れられていた。中学の頃、一度下して穂先のカバーを取払ったことがあるが、全くの片鎌槍であった。 しかし、清正が朝鮮征伐に用いたのだという祖母の話は、一笑にふしていた。 この甲冑と槍は、母が上京する時、村の神社へ預けた。祭礼の時自由に使って貰う為であろう。戦時中母が亡くなり、 戦後故郷へ帰った時、神主からその話をきいて、私が受取ったのだが、ひどく傷んではいても甲冑は櫃のまま残っていたが、 槍の方は、戦直後の命令を遵奉して穂先を供出したとかで、柄ばかりであった。ところが、若い頃は何の気なしでいたのだが、 この柄(一間半位だったと思う)貝鏤めの見事なもので、今更失った穂先が惜しまれた。 しかし柄だけではどうにもならないので村へ残し、甲冑だけ持って来た。 これは、萌黄糸威のあまり上等のものではないが、この市の物識りの鑑定によれば、桃山から徳川初期までのもので、 明らかに肥後加藤の家臣が着用したものだという。 刀は甲冑と一緒に蔵に放り込んであったが、中学の頃、時代劇映画などを見て来ては引っ張り出し、藁苞や大根などを切ったりしたものだ。 ところが卒業近くになって、同級生の中に刀の好きな男がいて、見せたら目を丸くして驚き、一度鑑定して貰ったらいいという。 鞘や柄などはなかなか凝ったものだとは思っていたが、如何なる人の作かなどは考えてもみなかったし、 第一柄を外して銘を見ようとしている友達の姿が、隠居染みて性に合わなかった。銘は何処へもなかった。 半年程して市に本阿弥何とかいう偉い刀剣鑑定家が来た時、彼があまりうるさくすすめるので、仕方なく蔵から持出し、 彼と共に会場へ出かけた。吉岡一文字だという。由緒をききたいというのだが、私にはさっぱりわからない。 ところが鑑定先生の側に、私の家をよく知っている人がいて、清正や忠広の話をしていた。 鑑定先生は肥後守のものに違いあるまいといった。 翌日学校へ行ったら、彼がアタフタとかけて来て、ポケットから地方紙を取り出した。見ると、トップ記事に私の刀のことが出ている。 吉岡一文字吉房とかいう代物だということや、由緒などが書いてあった。私はそんな事よりも、その記事が家の人達の目についたら大変だと思った。 持ち出したことは誰も知らぬからである。どうせ放り出してあるのだから、刀がどうのとは誰もいうまいが、そんな物騒なものを、 竹刀サックの中に入れて持ち運んだことは、どうも気がひける。しかし幸い、その新聞をとってなかったので、知られずに済んだ。 さすがに其後は、藁苞や大根を切るのは止めたが、何とか一文字などには興味もなく、相変わらず蔵に放り投げて置いたのだが、 早稲田へ入ってから、管弦楽部に居た関係上、軍教の演習の折軍楽隊の指揮を頼まれたのが縁で、 是永という配属教官の中佐殿と親しくなり、ふとしたことから刀の話をしたら、そういう名刀は白鞘に収めて手入れをせねばならぬといわれ、 夏休みに持ってかえった。中佐殿に見せたら「類稀なる名品だ。二、三日ゆっくり眺めたい」というので、貸してやった。 其後、中佐殿の命により、九段の刀屋へやって手入れをし、白鞘に収めた。 そこまではいいのだが、昭和十六年、知名の先輩や友人達と新劇運動を始めることになり、その資金造りの相談中、 長年アパートの押し入れの中に突っ込んである刀の事を口にしたら、すっかり当にされ、止むなく近所の刀屋へ相談に行った。 三、四十円にでもなれば、儲けものと思っていた。(当時の三十円は今の一万円以上だ) 刀屋の親父は刀を見て、 直ぐ日本銀行の役員をしていたという老人の処へつれていった。老人は刀屋と打合わせをしていたが、その場で三百円出した。 私は胆を潰した。 吉岡一文字吉房(かどうか知らないが、ともかく名品だったことは確かだ)が、如何なるものか薄々知るようになった今になれば、 誠に慚愧に堪えず、先祖に対して申し訳なく思っているが、その金をもとにして生まれた新劇の仲間達が、今各方面に華々しい活躍をしているのを思い、 多少の意義はあったものと諦めている。 長くなってしまったが、座像、甲冑、刀、槍は、いずれも祖母が分家する際、本家から貰ったもので、 いわば由緒ある品々であったに違いない。 |
|
(二) |
|
本家については、私が早大卒業直前まで生存していた祖母から、いろいろ聞かされた。以下はその覚書のようなものである。 明治十四年、明治天皇が東北巡行の折、本家へおいでになった。その折、祖母は御接待役をつとめたという。何でもその前に、 有名な歴史学者が二人来訪し、本家に伝わる品々や系図其他を綿密に調査した結果、肥後加藤の後裔間違いないということになり、 天皇のお宿に決ったのだそうだ。其後叙勲の話があったそうだが、当主の伊七郎正幸(私の曽祖父)が、 幾百年も世を忍んで来たのに今更と拝辞したという。 事実、社会的関連を途絶させられた時代の習性が、いつの間にか性格の中に深い根を下してしまった加藤家の人々には、 甚だ有難迷惑な話にちがいなかった。彼等が天皇のお成りに絡んだ時代のフットライトに、土の中から引っ張り出されたもぐらのように、 面映ゆく、とまどいした有様が、目に見えるような話も聞いた。 私は、早大へ入学する為に上京する迄、一日の大半を、この本家で過ごしたのだが、祖母から話を聞くまでは何も知らなかった。 私の少年期は、満州事変を中にはさんだいわゆる右翼的風潮の盛んな頃で、田舎でも事天皇に関しては、 些細な事でも立派な石碑を立て誇示していたものだが、本家には何もなかったし、又誰の口の端にも上らなかった。 私が祖母から聞いた話の中で面白いのは、毘沙門天の像の事だ、何でも清正があの長い烏帽子の中に入れて置いた守本尊とかで、 神棚の奥にあるのだという。加藤家には泥棒や不穏な者が忍び入ったことが一度もないし、忍び寄れないというのだ。 そういう者が忍び入ると、寄合いがあるように、大勢の人々のざわめきが聞こえるのだ。 そうした陳述をした泥棒が二人もあったという。それは、神棚に安置してある毘沙門天のなせるわざだと祖母はいうのだ。 誠にたわいのない話だが、その当時の社会構造や、時代に背を向けて生きなければならない加藤家の人々のことを考えると、 いろんな想像が成り立って面白い。私は、いつも、本家の大きな高い幕を張って中の見えない神棚を仰いでは、 祖母の話を想い出したものだ。 この毘沙門尊天立像は、一尺六寸の木製で、物識り達は鎌倉だとかいやそれ以前だとかいうが、そんなことよりも、 芸術的になかなか面白いものだと思う。一度在京の彫刻家の友人に見せたい。 尚、加藤村から新堀へ来る途中に、局(つぼね)という部落があるのだが、忠広の子に従った局が急病で亡くなった処といわれていることや、 加藤が新堀に落ち着く事が出来たのは、藩主酒井の内々の支援があった事、幕府の追及が厳しく、 遺物等を焼却した時代もあった事などを、祖母からきいた覚えがある。 しかし私は、加藤家を巡る品々や、伝説や、出来事よりも、次の事実に注目したいと思う。 その一つは、封建的な地方的な周囲とは全く異なった加藤家の雰囲気である。それは加藤家の人々の共通した特質によって、 積重ねられたものである。彼等は、恐ろしくハイカラで、趣味に徹した生活であった。いや、趣味とか物好というよりも、 それが生活の中心といってよかった。それというのは、あらゆる芸術、園芸、学究等、全く個人的なものである。 私が物心ついた頃から、本家には、凡そその当時に於ける最も新しい文化、スポーツ、娯楽の設備が、次々とつくられた。 そして、より新しい便利なものが出来ると、旧いものには何の執着もなく、どんどん取換えて行く。あらゆるものが、 時の流れと共に様相を変えて行くのだ。そしてその中からは、必然的にマンネリズムを嫌い、固定した生活習慣のない、 甚だアナーキーな匂いの漂う雰囲気が生れて来るのだ。それは、旧い地方的な封建的な周囲の社会とは、 全く無関心な租界であった。 勿論、金があればこそのことであるが、私が注目したいのは、彼等が何一つ社会に喜びを求めなかったということだ。 求めようとしなかったのだ。彼等の世界は、古い松林に囲まれた一万坪だったのである。彼等はその中で彫刻を造り、 油画をかき、楽器を鳴らし、小説や詩をつくって、ひそやかに生き続けて来たのだ。 私の家も同じような雰囲気であり、亡父などは最もその特質を身につけていたし、全く身分不相応な、 進んだ文化的生活を楽しんでいたが、本家の真似は出来なかった。しかし、一族であるので、何の遠慮もなく出入りし、 利用することが出来た。子供の頃から読みたい本は何でも読め、モーツアルトやシューベルトに親しみ、 十六ミリの主演を相つとめたりしたのは、仕合わせだったに違いないが、長じて社会に出、私が育った環境や雰囲気が、 如何に隔絶された温床であったかを、骨の髄まで知らされた。夢よもう一度とは思わぬが、昔を想い、加藤家の人々を考える度に、 その生活態度や物の考え方は、明らかに幾百年も幕府の目を忍ばせねばならなかった悲劇の歴史が、 つくり出してしまったように思えるのだ。習性がいつの間にか骨肉の中に深い根を下してしまったのであろう。 周囲に全く無関係に、許された小さな世界を、どんどん理想化して行ったことも、或いは背を向けさせられた権力や社会構造に対する、 一つの反抗の現れかも知れない。 もう一つは、加藤家が何でそんなに財産(といっても田地だが)をつくったか、全く不明なことだ。そういう家には、 何代目に何商売をやって儲けたとか、何をやって金を溜めたとかいう伝説や事実が、必ずあるものだが、 加藤家にはそれが無いばかりか、財産を増やした者も減らした者もない。昔から同じような生活を続けていたのだ。 莫大な田地からの収入は、ことごとくその小さな世界を理想化に近づける為に注ぎ込まれた。祖母からきいた伝説のように、 藩主酒井家より、始めから内々に広い土地を与えられていたのかも知れない。 以上は、村の人々の加藤家に対する特殊な敬意と愛情と共に、如何なる意図や経過や根拠でつくられたものかわかりにくい古文書や系図なるものより、 私にとっては、甚だ興味深いのである。 |
|
(三) |
|
私は、そんな環境に育ったからと云って、いや、そんな環境に育ったればこそ、古いものをほじくり返す興味は全くなかった。
清正の遺骨が発見されたとか、忠広の書がどうしたとか騒いでいる物識り達には、全く無関心だったし、
この時代にそんなものが何の意義があろうと、むしろ反発を覚えたものだ。 そんな私が、ふとした事から忠広の漢詩なるものにお目にかかったことが、忠広への興味を繋いだ第一の動機と云えるかも知れない。 決して優れた深いものではないが、透明なすがすがしさが感じられる。親の清正に似ず軟弱な不甲斐のない男のように思い込み、 悶々のうちに一生を終えた位にしか考えていなかった私には、甚だ意外なものであった。 そのうち、忠広の遺臣達が、始末の希望を書いて、酒井摂津守(忠広の監視役)に差出した古文書を読んで、増々興味を覚えた。 全員が、行先と、行先のない者は酒井家に仕えたいと、何ものにも捉われず、希望を打ち出している。そして、 各々その希望通りに身を処している。私は、この古文書を読んで、現代の息吹を感じた。何と云う明るい民主的な始末ではないか。 加藤家は、表向き、忠広の逝去を以て断絶だ。遺臣は、いずれも、主君と生死を共にしようという家臣たちの中から選ばれた、 忠広とは殊に深い関係の者ばかりである。そして、世は鴎外の「阿部一族」などにある如く、殉死が盛んに行われた時代であり、 堅苦しい士道が横行していた。 忠広と云う男は、よほど偉い(当時の侍道から抜け切った)人間か、それとも話にならぬ程くだらない人物か、 どちらかであるわけだが、その筆跡や詩などからみて、誰一人後追いせぬ程つまらぬ男とも思えない。 これは、もしかすると、現代に生かしていい人物なのかも知れないと思った。 其後、私は、忠広の配所のあった丸岡や、忠広に与えられた一万石の領民の子孫達が、未だに忠広の徳を称え、 その命日には集まってお祭りをしていることを、目の当たりにする機会を得た。そして、驚くべきことには、百姓たちが、 忠広の遺品を持っていたり、配所の木々から、いろんなものをつくって、大切に保存しているのを知った。忠広への敬慕が、 多くの人々の間に、ひそやかに、つつましく、しかも確かな根を持って、継承されて来たのである。 私は、忠広の生涯を画いてみようと思うようになった。古いものをほじくり返すのではなく、 あまりにも人口に膾炙した父清正の陰にかすんでいる忠広と云う悲劇的な男に、新しい人間の息吹を与え、 それを徹底的に追いかけてみようと思った。 私は、忠広に関する古文書、文献を漁り始めた。やがて、私の中には、忠広への愛情と共に、その人間像と一つのストーリーが、 次第に型造られて行った。 かくして私は、戯曲「身似明星西又東」の執筆にとりかかったのである。 |
|
(片山丈士「身は明星に似て 附記」より) |
(C)2016 身似明星