

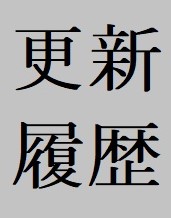
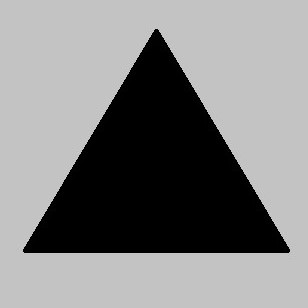

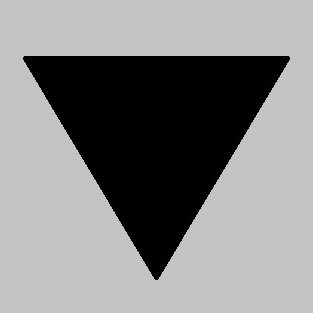

HOME>清正の生涯
↑
| この項では、清正に関する逸話を検証した「清正巷談異聞」を紹介します。歌舞伎や絵本の題材として取りあげられ、 そのイメージが強く一般には広まっていますが、実際はどうだったのでしょうか。 もちろん当時の正確な事はわかりませんが、多くの古文書や当時の状況から、 真実に近いと思われるものを推測する事は可能です。 ”清正の生涯”の中でも一部触れていますが、大変興味深い内容なので、別項にしてここで取りあげることにしました。 おそらく「加藤清正」出版後の昭和40年代にまとめたものと思われます。原稿しか残っておらず、 雑誌等に発表されたものなのかどうかも分かりません。 |

珍齋呂雪:加藤清正朝鮮国ニテ猛獣ヲ退治スルノ図 |
|
清正がいわゆる虎退治をしたことは、事実である。秀吉から清正に送った感状にも、虎が送られたことが書いてあるし、 朝鮮の役の真中、秀吉の勘気をうけて帰朝した清正は、地震(いわゆる地震加藤の物語の)の後、引見を許されて、 虎の皮五枚その他の土産を持って登場している。また清正自身も、幾枚かの皮を持っていたようだ。これらの虎は、 数にしてどのくらいになるかわからぬが、清正陣で仕止めたものであることは間違いない。 もちろん清正一人で退治したものではないが、清正自身も退治者の一人であることは事実だ。当時、 秀吉はじめ多くの国内諸侯は虎を珍重し、在鮮諸将は争って虎狩りを行ったようだから、 他陣からの送りものなどということはありえない。 虎狩りはいつ、どこで行われたかということも、たしかな記録は残ってないが(前に書いた秀吉から清正に送った感状も、 四月十二日とあるだけで、年のことはわからない)朝鮮に虎がいたことは間違いない。 ある夜、清正陣背後の山から大虎が出て来て、馬をさらって逃げた。馬の啼き声をきいて飛び出した将兵は大いに驚き、 弓や鉄砲を持って追いかけようとしたが、虎は山へ隠れて見えなくなってしまった。それから数日後、また大虎が現われ、 上月左膳という小姓を喰い殺した。そこで清正は、夜明けを待って山を包囲し、鐘太鼓を打ち鳴らして狩り立てた。 やがて深く繁った萱原の中から、七尺余の大虎が、たけり狂って飛び出した。 清正は大きな岩の上に登り、みずから鉄砲を取って狙いを定めた。虎が十四、五間ばかりのところに迫ると、 近習たちは筒先を揃えて一斉射撃をやろうとする。清正はそれを押しとどめ、毛を逆立て、 口を開いて突進して来る大虎を引き寄せて鉄砲を放った。弾丸は、虎の咽喉の中へ撃ちこまれ、 さすがの猛虎もどうと倒れたが、また起き上がろうとする。清正はやにわに鉄砲を捨てて槍をとり、 突き刺して仕止めた。 槍で仕止めたとか、その時虎から噛まれて十文字槍が片鎌になったとかいうのは、もちろん講談で、 鉄砲で倒したには違いないが、槍は全然使用しなかったかというと、そうでもなさそうだ。当時の鉄砲は火縄銃で、 引き金を引けば簡単に連発できるような代物ではないうえに、虎は一発で瞬時にしてコロリと参る代物でもない。 急所に命中しても、ちょっとの間はバタバタとあばれるだろう。槍をふるったというのは、この時ではないか。 鉄砲で倒し、槍でとどめを刺したのではないか。 |

清正が退治した虎の頭蓋骨 (徳川美術館HPより) |
|
在鮮諸将のうちで、もっとも早く虎を秀吉に贈ったのは、亀井真矩のようだ。文禄元年秋ごろで、
年末には秀吉から虎到来の感状を受けている。面白いのは、退治という言葉である。
退治というのは悪いことをしたものを懲らしめることで、虎狩りと虎退治とではニュアンスが違う。
虎が清正陣中の小姓や馬を喰い殺したのが、本当かどうか立証することはできないが、
そういうことがあって虎を仕止めたなら、退治という言葉にふさわしく面白いではないか。 前述のように在鮮諸将はさかんに虎狩りをしたので、虎を仕止めたのは清正ばかりではないし、清正陣でも、 清正自身よりも家来たちが仕止めた方が多かったに違いない。亀井のように、虎の一番狩りもいる。 それなのに虎退治というと、清正の特許のようになってしまった。人気とは恐ろしいものである。 虎退治そのものは、清正のすぐれた鉄砲技術、胆力を示す以外、さしたる意義はないのだが、 清正はこれによって、はなはだユーモラスな存在となり、桃太郎や金太郎の仲間に入れられてしまった。 童話の世界のヒーローになったのだ。地下の清正もこれには苦笑を禁じ得ぬものがあろう。 |
|
(文:片山丈士「清正巷談異聞」より) |

歌川豊宣:賤ヶ嶽大合戦之図 賤ヶ岳七本槍 (パブリックドメイン美術館HPより) |
|
清正が賤ヶ嶽の七本槍の一人であることもよく知られている。賤ヶ嶽の戦は、 天正11年(1583)近江賤ヶ嶽を中心に行われた秀吉と柴田勝家との戦で、 信長亡き後その遺産を誰が受け継ぐかという極めて重大な戦闘であった。 この戦で敗れた勝家は北庄城で自刃し、秀吉の全国制覇の基礎が築かれたのだが、 清正もこの時の働きが出世のいとぐちになったといっていい。 前年(1582)光秀討伐を終えた秀吉は、同年11月には対立状態にあった勝家、織田信孝(信長三男)、 滝川一益等と和を結んだのだが、間もなく長浜城を守っていた勝家の義子勝豊を攻囲し、 戦わずして降伏させ、賤ヶ嶽に三つの砦を築いて勝家の来攻にそなえた。 この年(1853)の正月には、秀吉は書を諸将に送って来参を求め、2月には一益を討つべく伊勢に入った。 一方勝家は、越中富山の城主佐々成政を上杉景勝のおさえに残し、3月には近江に入り、柳ヶ瀬北方に陣を布いた。 秀吉は、勝家の出兵をきき、信雄(信長次男)等に一益攻撃を任せ、みずから大軍を率いて木ノ本に到着したのだが、 両軍ともいたずらな攻撃は不利とみてにらみあいの状態が続いた。 信孝が一益支援に起ったことをきいて、そのうち秀吉は岐阜城攻撃に赴いた。ところがその隙に乗じ、 勝家側の佐久間盛政が、秀吉が築いた賤ヶ嶽周辺の三砦を急襲し、二砦を陥落させた。勝家は、 盛政に深入りせずに引返すよう再三命じたが、盛政はきかずに滞陣した。これが敗戦のきっかけとなったといっていい。 秀吉は大垣にてこの報をきき、「柴田一党ことごとく誅伐の時来る。これ天の恵みだ」と打ち笑ったという。 先方から仕かけて来るのを、すでに計算に入れていたものと見える。彼は直に勇躍して木ノ本に引きかえした。 そのスピードはおどろくべきものであった。秀吉得意の戦術である。 賤ヶ嶽を包囲していた盛政は、秀吉到着を知って急いで退却しはじめたのだが、時すでにおそく、 すでに包囲態勢をととのえていた秀吉は、高地から鉄砲の雨を浴びせ、浮き足立ったところで突撃を命じた。 このとき秀吉は、扇をサッと打ち開き「近習の若者ども攻めかかれ、(勝軍に軍法は時によりけりだ。)真っ先に槍を入れよ。 手柄は仕放題だぞ」と大音声で叫んだという。 清正をはじめ福島市松(正則)、加藤孫六(嘉明)、片桐助作(且元)等若い近習旗本は、突進した。 世に賤ヶ嶽の七本槍というのは、この時抜群の働きをした前記四人と脇坂安治、平野長泰、糟屋助右衛門尉、 桜井佐吉、石河兵助等をいうもので、秀吉はこの九名に各々一番槍の感状を与えている(石河兵助だけは戦死したので、 弟長松に与えている)。また褒美として福島に三千五百石(五千石ともいわれている)、他はいずれも三千石を与えられ、 物頭を命ぜられた(石河兵助弟は一千石)。 七本槍というのは、秀吉が名づけたわけではない。前にも小豆坂七本槍という言葉もあるので、 誰いうことなく生まれたものであろう。後年桜井と石河を除いたり、正則を特別扱いにしてその代り桜井を加えたり、 桜井、石河に伊木半七を加えて「三振太刀」という別称を与えたりしているが、九人の感状はほとんど同文であり、 同等の恩賞を受けているところをみても、九人に段階をつけたり、特定の人を除いたりするのは、まことにおかしい。 これは、七本槍の七本に人数を合わせるためにつくられたものであろう。七本槍の七本というのは、 大約の数をいった言葉で、必ずしも七人のことではないと解すべきではないか。 清正は、後日側近に、この時のことを次のように物語ったという。 「飛び出そうとすると、太閤がキッと見据え、『虎之助、螺(ほらがい)を吹け』と仰せられた。 わしは功名にはやって、おくれてはならじと思い、聞こえぬふりをして二、三間進んだが、 ふと緊急の折に臆病者の吹く螺はよく鳴らぬといわれることを思い出して立止った。 今わしは、心臆して吹かぬのではないかと太閤はじめ多くの人々に思われては、 弓矢の恥と気がつき、戻って貝を取り、いかにも静かに吹き上げ、吹き終わって馬に乗り、急いで進んだ」 まことにいい話である。血気に逸って飛び出そうとした清正を留め、「螺を吹け」といった秀吉、 ハッと気がついて静かに吹き上げた清正、両者の情愛と嗜みがにじみ出ているばかりか、 清爽な一幅の画を見る思いである。 |
|
(文:片山丈士「清正巷談異聞」より) |

豊原国周画『増補桃山譚』(地震加藤) 加藤清正に扮する9代目市川團十郎 (国立劇場蔵) |
|
芝居で有名な「地震加藤」は、朝鮮の役の最中におこったことだ。慶長元年、清正は秀吉の怒りを買って、 朝鮮から召還されたのだ。それは小西行長、石田三成等の画策によるものであった。 石田三成は、いうまでもなく秀吉側近第一号で、小西行長はその片腕であった。両者と清正は、 決してウマの合う仲ではなかったし、講談では、清正と行長が先鋒を争ったとか、京城一番乗りを競ったとか、 ことごとに対立させて、面白おかしく書き立てている。なるほど両者の間には、いろいろと個人感情もあったろうし、 その他にも事情があったかもしれないが、対立の最大の理由は講和をめぐる争いであった。清正を朝鮮におくことも、 また秀吉に会わせることも、絶対に回避しなければならない理由が彼等にあったのだ。 行長と宗義智は在鮮部隊の中の外交係であった。宗は対馬領主で朝鮮の事情に明るく、行長の娘を妻にしていた。 彼等は、三成と緊密に連絡をとりながら、講和の交渉をすすめていたのだ。ところが彼等がすすめている講和は、 肝心かなめの明帝、朝鮮王、秀吉をつんぼ桟敷に祭り上げた複雑奇妙なものであった。 明の外交担当者の石星やその使者の沈惟敬等と、何とかうまくごまかして和平に持って行こうとやっきとなっていたのだ。 彼等すなわち欺瞞講和の主役達がそのような役をつとめるようになったのには、それなりの理由はあった。 秀吉の明、朝鮮に対する態度がひどく非現実的であったこと、明、鮮も日本に正しい認識を持っていなかったこと、 別の言葉でいえば、秀吉と明、朝鮮との間の相互認識、評価がとほうもなく相違していたことだ。 お互の要求を正確に伝達したら、和議不成立は火を見るよりも明らかであった。戦を好まぬ彼等としては、 なんらかの手を打つより仕方がなかったであろう。そこに策謀が生まれたわけだ。 といっても、彼等に同情しているわけではない。なるほどワンマン秀吉の権威は絶大で、その命に逆らい、 気色を損ずることを、諸侯は大いに恐れたであろうことはよくわかるが、明、鮮の実状を伝え、 ワンマンの桁外れな認識を正しく導くことは、彼等以外の誰が成し得よう。権威の前に無力化し、 姑息な手段を採らねばならなかったことは、責められるべきであろう。 清正は、朝鮮の傑僧松雲と親しくなり、つきあっているうちに、行長等の講和の実態を知ってしまったのだ。 これは文禄三年のことで、その前の年に明使が来日し、秀吉がこれに講和の条件を示したのだが、 それが朝鮮側に何一つ伝えられてなかったのだ。松雪を通じ清正から秀吉の条件をきいた朝鮮側は大いにおどろき、 明に問い合わせた。石星は朝鮮側をうまくなだめ、一方あわてて行長に通報した。ここで行長も、 清正がおぼろげながら講和のからくりを感知したらしいことを、知ったのだ。 其後、清正の家臣が明使の先導者を追払ったり、 明の正使が逃走したのも清正の家臣が行長等のカラクリをしらせたのだというウワサが立った。 行長等にとって、こうした清正の存在が、はなはだ具合の悪いものであることはいうまでもない。 なんとか朝鮮から追放しなければならないのだが、それには秀吉を動かすしかないのだ。 これは明らかに陰謀であった。彼等はこの陰謀を実行するために、水も漏らさぬチームワークで秀吉を動かした。 清正への召還の使者が到着したのは、慶長元年四月である。清正は、慶長元年六月九日、伏見に到着したのだが、 秀吉は申し開きはおろか、目通りも許さず、伏見の私邸で罪を待つよう命ぜられた。清正は愕然とし、あらためて三成、 行長等の張りめぐらした陰謀の網が、自分を幾重にもとり囲んでいる実態を悟ったのだ。しかし、 なんとしても秀吉に会わねばならない。それが何よりも先決である。いろいろ考えた末、 三成の同調者で固められた秀吉側近の中で、比較的親交のあった増田長盛に、 ともかく秀吉と会うことに骨を折って貰おうと思い、その私邸を訪ねた。 増田はちょうど来客中とかで、 取次ぎの谷市助に用件を伝えると、市助は増田の言として、 「石田三成と仲直りさえすれば、明日でもその旨を三成に伝え、とりなしてやろう」 と伝えた。清正は憤然として、 「三成とはたとえこの身が切腹するとも、仲直りはしない。自分が朝鮮からはるばる来訪したのに、 出ても来ぬような者に、今後一切頼みはしない」 と、席を蹴って退出した。当時、清正は切腹を命ぜられるのではないかと取沙汰されていたというから、 いわばたいへんな危機であった。秀吉と会う機会を持つことは、危機から脱出できるかもしれない唯一の手段であった。 が、清正はみずからそれを投げた。藁を掴もうとしなかったのだ。彼は静かに伏見の邸に閉じ籠り、仏の前に端坐して、 法華経を読み続けたのである。 地震が襲ったのはこの時のことだ。正確には七月十二日真夜中、清正はその夜も遅くまで仏間に篭って法華経を読誦し、 ようやく寝所に入ったばかりであった。彼は起き上がって素早く甲冑を身に着け、槍を取り、三百人ほどの家臣を連れて、 真一文字に伏見城へ向かった。これがいわゆる「地震加藤」として世に広まった物語りである。 この時の地震はすこぶる大きなもので、七月十二日の午前零時にはじまって、十日も余震が続き、 伏見城はじめ諸侯の屋敷、京、伏見の民家はほとんど倒壊し、死者はその数を知らずという有様であった。 さて、清正主従は息せき切って伏見城にかけつけ、清正は外から高蔵主を呼び、 「大地震なので、万一上様が家屋の下敷きになられるようなことがあれば大事と存じ、 足軽に梃子を持たせ、参上仕った」 と告げた。結局これが秀吉の心を和らげ、弁明の機会が与えられ、勘気赦免となったわけだが、 行長との対立についての弁明だけで秀吉が許してしまったので、講和のことにはふれないままになってしまった。 しかし、この約一カ月半の後、秀吉は明書によって講和のカラクリを察知し、行長が殺されそうになったのだ。 そして和議は決裂し、後役(慶長の役)が始まる。 地震加藤の物語は、現代では小利口な何か演出の臭いを感ずるむきがあるかもしれないが、決してそうではない。 清正の行動は桁はずれなものであった。閉門中の身で武装し、家来を引き連れ外出することは、 天下の掟を破ることであり、また秀吉の権威に対する挑戦でもあった。まして伏見城へ向かったのである。 秀吉が素直に受け取ってくれなかったら、さらに罪を重ねることになる。計算の立てようもない行動なので、 演出ではできないことだ。 静かに天命を待っている清正の心境は、澄み切っていたにちがいない。世俗的な感情を超越した彼の脳裏には、 やはり今日の自分を生育してくれた秀吉への素直な心情が沸き上がっていたのであろう。清正にとってこの行動は、 最も己に忠実な、極めて自然なもので、世俗的な作為や意識的な夾雑物が入る隙間のない、 それなりに充実したものといえる。悲運のどん底にあって、少しもジタバタせず、 静かに経を誦えて日を送っている清正であればこそ、生れ出た純粋な行為といえよう。 秀吉が動かされたのも、そこにあるのだ。 |
|
(文:片山丈士「清正巷談異聞」より) |

二条城 |

大広間 |
|
芝居でよく知られた清正譚のもう一つは、二条城会見だ。 また清正が家康に毒まんじゅうを食わせられて死んだというような話も広く流布されている。 この二つのことは密接にからみ合っているので、一緒に述べることにしよう。 慶長10年、家康が将軍を秀忠に譲り、はじめて秀頼に上洛を促したおり、大阪では大いに驚き、 かつ激怒した。それは、家康が秀頼に政権を返す意志など微塵もないことを悟ったからであり、 そのうえ上洛を促す非礼に対してである。上洛を拒絶した大阪方は、年とともに警戒を強くし、 家康もまた以後秀頼を訪ねることをしなかった。両者の間は、次第に重苦しい空気になっていったのだ。 家康は、慶長16年3月、大軍を率いて西上し、二条城に入ってふたたび秀頼に来訪するよう促した。 しかし大阪方では、なかなか承諾の意を与えなかった。大阪方の中心は、いうまでもなく秀頼の母淀君であった。 どうしても来訪せよというなら、秀頼とともに自害するとわめいたという。しかし家康はなかなか諦めようとせず、 次は高台院(北政所ねね)に意を伝えて助力を依頼した。京都東山の高台寺で亡夫の供養に明け暮れていたねねは、 大阪へ下って淀君に上洛を促したが、これまた承諾を得るには至らなかった。両者の対立で、大阪近辺は次第に騒然とし始めた。 庶民は、必ず近く天下の乱が起こると慌てふためいたという。片桐且元も大阪城へ駆けつけ、淀君に秀頼の上洛を諫言している。 清正と浅野幸長が二条城に呼ばれたのは、こういう険悪な様相が漂い始めた時であった。この時家康は、 二人の愛児を人質にやってもいいから、秀頼を上洛させるようにと頼んだという。 家康が執拗に秀頼の上洛実現に食い下がったのは、それが徳川の天下固めに最善の策であることと信じたからであろう。 かつて己が豊臣家に示したように、上洛後の秀頼も、幕府の一大名として服従することを願っていたに違いない。 この時家康は70歳になっていた。自分の目の黒いうちに何とかしなければ、幕府にとって必ず禍根になろう。が、力に訴えれば、 勝負は別としても、天下の争乱になることは間違いない。戦は避けねばならない。 こうした計算が家康の執念を支えていたのであろう。 清正と幸長は、連れ立って大阪城へ入り、 「この際は忍び難きを忍び、上様が御上洛遊ばすことこそ、豊家の為に最善の道と存じまする。上様の御身はかく申す清正、 幸長が一身にかえてもお護り申しまする」 と淀君を説得した。淀君もついに折れて、秀頼の上洛になるのだが、清正と幸長はこの言葉通り、身命を賭して警護に当たった。 会見は、3月28日に行われ、秀頼は川船で伏見に出、伏見からは駕籠で二条城に入った。 淀川の両堤には清正と幸長の配下が三百騎ずつ警護し、伏見から二条城の三里の間は、清正と幸長が青竹を杖にし、 徒歩で秀頼に駕籠の両側にぴったりつき添い、その前後に一騎当千の士が多数随行した。 |
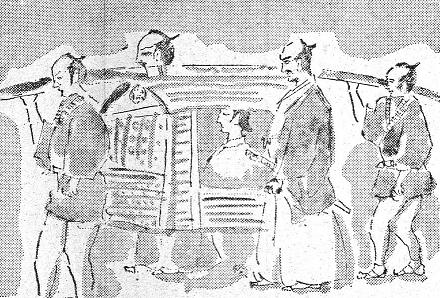
連載清正挿絵より:絵高橋裕一 |
|
無事会見を終えた秀頼は、豊国廟に参詣し、大仏の工事を見廻って伏見に出たのだが、清正は屋敷前の川中に船席を設けて秀頼を招き、
善美を尽した食事を献じ、さらに川下三町の左右を竹で囲って随行者の席をつくり、下々のものまで残らず食事を供したという。
伏見から船で大阪へ帰る秀頼を見送った清正が、懐中の短刀を取り出してホロホロと涙を流し、 「われ今日太閤の厚恩の万分の一に酬いることが出来た」 と泣くところは、芝居のクライマックスで、広く世に喧伝されている。この時清正が懐中深く秘めていた短刀は、 かつて秀吉から拝領したもので、秀頼の身に万一危害が加えられるような場合は、これで家康を刺す決心であったという。 会見の際、刀は預けるので、肌身につけたわけだ。 この芝居のようなことが、果たしてあったかどうかは、わからないが、清正が異常な決意で短刀を懐中にしたこと、 大任を果たして亡き秀吉を偲び、感無量の思いであったことは、容易に推察される。 そして、この芝居がいささかも誇張されたものでないことを、知ってもらうためには、もう少し説明を加えねばならない。 清正は、明らかに、淀君を中心とする大阪方とは意見を異にしていた。彼は幼少の頃から秀吉に仕え、数々の戦場に出、 戦国乱世の無常を骨に滲みて味わっていた。そしてまた、秀吉がどのようにして天下を掌中にしたかも、 誰よりもよく知っていたに違いない。明智を亡ぼした秀吉が、信長の後継者として三法師を奉じ、 一門の諸将と力を合わせて後見することを自ら誓いながら、天下を握った後、どのようなことをしたかということも・・・・。 戦国をくぐり抜けて来た武将達は、善悪の批判は別として、実力のある者が容赦なく政権を略奪することが、 常道化しつつあることを体験していたのだ。秀吉の遺命などは、家康の意向次第で消え失せてしまうことを知っていた。 信長は秀吉にとって大恩ある主君であるのに、秀吉と家康の間には、そのような事情が何もないのは説明するまでもない。 その家康が関ケ原以後秀頼に示した態度は、冷酷無惨なものでは決してなかった。名実ともに天下の政権を握ってからも、 摂、河、泉三州六十五万石を給して家名を存続させていたのだ。 清正は家康という人間を熟知していたに違いない。決して無謀な無益なことを好まず、 己に忠実な人間に危害を加えるようなことはしない反面、己の政権の禍根となると睨んだ異分子は、 いかなる手段をとっても抹殺するであろうことを・・・。この家康の性格と強力な実力、 その下でひたすら平和と領土保全を希求する諸侯の動向、当時の思潮などを考えると、豊臣家を存続させる方策は、 幕府の異分子になることなく謙虚に家康に従う以外道がないことは、清正ならずともわかりきったことであろう。 そうするには、淀君は世の移り変りをよく認識し、秀頼は秀吉の遺児としての虚名を捨て、 宿命的な対立関係を一日も早く解消しなければならない。こうした考えは、高台院も幸長も同じであったろうし、 片桐且元等大阪に駆けつけた諸候の中にも、同じ考えの者がいたに違いない。家康はこの時、もし秀頼が上洛を拒否したら、 豊臣の滅亡政策に踏み切る覚悟であったというから、清正の見通しは正しかったといえよう。 さて、清正がこの二条城会見に情熱を傾けたゆえんのものを解説したのだが、先にも書いたように、同じ考えの人々は他にもいた。 この会見を成功させたこと自体もたしかに意義があったのだが、清正の真の面目は、この会見に示した態度であった。 態度に現われた決意であった。家康が、秀頼の上洛を、愛児を質にしてもと清正に頼んだことは、 彼が清正の豊臣家の将来に対する考えを見通した左証であるが、一面清正に、 大阪方につながる有力者としての認識を持っていることを示している。清正は、この家康の認識を恐れなかった。 彼が単に保身にきゅうきゅうたる人物であるならば、家康側の使者として秀頼の上洛を促し、 その回答を家康にもたらしたに過ぎなかったであろう。清正はこの会見で、敢然と秀頼側に立ったのだ。 その手兵を動員して警戒に当たり、みずからは秀頼の側を片時も離れずに万一に備えた。 清正は、家康に向かって無言の叫びを放ち続けたのだ。 「こうして貴殿の要請に従った秀頼様を、よろしくお頼み申す。それでもなお貴殿がこの秀頼様の滅亡を計るならば、 忍耐はもはやそこまででござる。この清正、秀頼様とともに、天下の軍勢を引き受け申そう」 清正は、秀頼を上洛させることによって家康の心を和げ、決意を行動で示すことによって家康に無言の圧力をかけ、 豊臣家を護ろうとしたのだ。そのことがわからないと、清正の涙がかすんでしまうことになる。 |

|

|

|
| 秀頼 |
二条城の清正 (吉右衛門) |
家康 |
|
二条城会見を終えて海路帰国した清正は、船中で病を得、五月二十七日に熊本に着いた時は、すでに重体であったようだ。
その後約一ヶ月闘病を続けたのだが、ついに薬石効なく、奇しくも誕生日の六月二十四日に永眠した。享年五十歳であった。
清正の死因は、二条城で家康に毒をもられたからだという話が、昔から広く流布されている。
古書が伝える毒殺説はいろいろあるが、その中から一つだけ書いてみよう。 清正は、城中で二つの饅頭を手にとり、一つを食べ、一つを懐中にし、それを帰途船中で茶坊主にやった。 茶坊主はたちまち黒血を吐いて死んだので、清正は覚悟を決めた。清正は勇猛の士だから毒の廻りも遅く、 次第に体が弱くなって亡くなったというのだ。他の話も、毒を仕込んだのは家康の忠臣平岩親吉であったり、清正だけでなく浅野、 池田等も同じ手でやられたのだというようなちがいはあっても、講談的で非科学的なところは共通している。 あの深謀遠慮な家康が、そんなみえすいたことをやるとは思われないし、 またそういうじわじわと効いてくるような毒(諸説同じ)についても、甚だ疑問が多いので、事実無根であろう。 がしかし、こういう説が流布されるにふさわしい条件はたしかに存在していた。 まず第一は、清正の死は二条城会見後わずか三ヶ月である上に、甚だ奇妙な病であったからだ。船中で発熱して次第に重くなり、 熊本に着いて間もなく言語障害をおこし、亡くなるころは身もこがれ黒くなったと古書にある。(脳溢血のよう) 第二は、家康が大阪を攻めるまでの間に、豊臣につながる大名がバタバタと亡くなったことである。 すなわち清正の亡くなる二ヶ月前に浅野長政、清正と同月に堀尾吉晴、慶長十八年には池田輝正、 清正とともに秀頼を守護した浅野幸長、翌十九年には前田利長が亡くなっている。しかもいずれも家康より若い。 第三は庶民の家康観である。タヌキおやじのニックネームで呼ばれた家康が、腹黒い策謀家として、 庶民に不人気であったことはいうまでもない。家康なら、それくらいのことはやりかねないと、 庶民は思ったにちがいない。 こうした諸条件がからみ合った中で、すべてが家康の都合のよい世の移り変わりに腹の虫がおさまらない庶民の間から、 清正毒殺説は極めて自然に生れ出たものであろう。 |
|
(文:片山丈士「清正巷談異聞」より) |

|
|
清正というと頬髭をのばして仁王のような巨人を連想する人が多いと思う。たしかにそういう画も多いし、 鬼将軍、朝鮮征伐、虎退治等の言葉からは、そうしたイメージがふさわしい。が、実は、 清正の容姿について決め手となるようなものは何もないのだ。 いろんな点から推理すると、清正は、 当時としては背が高い方だが、巨人といえるようなものではなさそうだ。170センチ前後であろう。 体は一見痩せがたにみえても、裸になると筋骨隆々としているというような、 鍛え上げられた体に共通なたくましいものであったろう。 顔は、どちらかといえば面長で、目鼻立ちがはっきりし、いわゆる彫の深いもののようだ。 恐らく日常の清正は、講談本や庶民のイメージとは似つかわしくない、静かな落ちついた内面的な風貌をしていたのではないか。 頬髭をのばしていたのは事実だが、それは朝鮮の役からのことで、慶長八年、従四位下肥後守に任ぜられた頃に、 剃り落としたようだ。だから、朝鮮の役前の戦や二条城会見等で、清正が頬髭をのばしている画や記述があるとすれば、 それは事実と異る。 |

(妙行寺HPより) |
左の画像を所蔵している妙行寺は、清正生誕の地(名古屋市中村公園内)にあって、清正の開基した日蓮宗の寺院である。
清正は、慶長十二年二月末から同年八月末までの間、名古屋城の大天守、小天守の石垣造築のため、
万松寺(現桜天神の辺)境内に宿舎を新築して住んでいた。帰国の折、その宿舎の一部の古材を生誕の地に運び、
建立したのがこの妙行寺であるという。 清正は、慶長十六年三月二十八日に、秀頼を護って、家康との二条城会見に立ち会ったのだが、その前に京都で、 絵師を熊本に招いたという。清正が会見を終えて熊本に帰ったのは、五月二十七日であったが、絵師はとうに到着していた。 すでに病に侵されていた清正は、病床に絵師を招き、衣冠束帯をつけて端然と坐り、己の像を描かせたという話が伝えられている。 この画像が、この話のものかどうかは、話自体の真否が不明なので、なんともいえないが、 賛が清正菩提所肥後本妙寺の当時の住職日遥上人のものであり、清正の亡くなった年月日と「前肥州太守」とあるところを見ると、 これは極めて注目に値する。すなわち、病床で描かせた画像に、清正没後、 菩提をあずかる日遥上人が書き入れたものとの推定が成立するからだ。たとえこの話を否定してかかったとしても、 賛がまぎれもなく日遥上人の筆であることや画像の時代色から、やはり注目すべきものであることには変わりないだろう。 |
|
(文:片山丈士「清正巷談異聞」より) |
|
|
清正の廟のある肥後本妙寺には、古来癩患者の参詣が多く、特に大祭の折などは、全国から群集したという。 それは清正自身が癩であったからだなどという説もあるようだが、それは間違いで、 朝鮮の役の凍傷兵と関係があるようだ。 清正軍は朝鮮の役の最初の年、極寒の咸鏡道で越冬したために、多数の凍傷者が出た。 清正は、これ等の患者を次々に送還し、病舎をつくって療養につとめさせたという。 凍傷者は、一見癩患者と似ているところから、清正は癩患者に手厚い保護を加えているということになった。 癩患者は悪くなる一方だが、凍傷の方は手足を失うことはあっても、 病状がどんどん進んで死に至るようなことはなかった。癩患者はその様子を知って、清正を癩治療の神様のように思い、 群集したのだという。 |
|
(片山丈士「清正巷談異聞」より) |

熊本三賢堂の清正公像 朝倉文夫作 |
|
現在熊本県内には、清正を祠る加藤神社がたくさん建っている。だいたい神社というようなものは、 権力を背景にして創立されるものが多いのだが、この加藤神社は、農民みずからの意志で、 みずからの手で造り上げたものなのだ。その上、いずれも忠広(清正の嫡子)が幕府の弾圧によって肥後を追われた後、 つまり細川時代になってから建立されたもので、むしろ清正を祠る神社を設立することが、時流に沿ったことではなかった。 清正は、まことにすぐれた治政者であった。産業の開発、貿易、文化、築城等その業績は各方面にわたっているが、 中でもその卓抜な創意工夫による水利土木事業は、その規模、技術、徹底さにおいて、 一藩主としては空前絶後のものであろう。清正入国前の肥後は、まさに自然の暴威に任されていたといっていい。 清正は、目を閉じるまでみずから先頭に立って、この国造りに献身した。ここで全容を詳述することは出来ないが、 ともかくその工事は治水、灌漑のための川の堀り替え、護岸工事、灌漑池の構築、海辺の防備、干拓、新田の開発、 道路の整備等あらゆる部面にわたり、ほとんど肥後全域に及んでいるのだ。しかも、その施行は堅固無比であり、 いたるところに卓抜な創意工夫がなされている。 この清正の国造りによって蘇生し、生活基盤を確立した領民(特に農民)が、清正逝去後、個々にその霊を祠り、 遺徳をしのんだのに始まり、年とともに追幕の情止みがたく、相語らって社を建立したというのが、 加藤神社の設立過程なのである。したがって、熊本城内にある神社の他は、いずれもささやかなものだ。 が、これ程清正にふさわしいものはあるまい。 |

廻江新村 加藤社 |

甲佐町 加藤神社鳥居 |
| (片山丈士「加藤清正 下巻」より) | |
|
清正が、肥後の人々の心の中に、四百年後の現代なお生き続けている秘密はここにあるのだ。 単なる名君であったというだけなら、三代も過ぎれば忘れ去られてしまうにちがいない。 が、肥後の人々は開発した土地に住み、その広大な遺業の恩沢を現在も受け続けているのだ。 そこに尊敬と感謝と親愛の情が生まれるのは当然のことである。 清正は武術に勝れ、戦場では数々の働きをしたが、戦略戦術にすぐれていたわけではない上に、 戦はすべて他動的なもので、みずからの欲望で己の家来を駆使したことはなかった。 彼は諸国を攻略し、天下を望むようなことはしなかった。秀吉が鰻登りに出世したからよかったものの、 そうでなかったら、自分の力を生かし、怪物どもの間を巧みにくぐり抜け、 大国の領主になるような器量は持ち合わせていなかったであろう。従って清正は、戦国武将の典型ではない。 典型的な戦国武将とは、遠大な野心も権謀術策もなくてはならず、清濁併せ呑む度量も必要であろう。 淡白で誠実で直情一徹な清正には、求め得べくもない。 清正がそういうものを求めていたのに、到らなかったのではなく、求めなかったのだ。 柄が違うのだ。だから清正が戦国武将の典型ではないといっても、それは彼を低く評価したことにはならない。 清正は英雄ではなく偉人であった。彼の真骨頂はその人間と治政にあった。誠実で信義に厚く、 何よりも人倫を尊重したというような数々の美点を持ったその人間と、文字通り領民のために献身したその治政である。 清正といえば、ともすれば好戦武将の典型か、封建時代の遺物のような認識を持たれているキライがある。 頬髭をのばした仁王のような巨人を連想する人も多いだろうし、また鬼将軍、朝鮮征伐、虎退治等の言葉からは、 そうしたイメージがふさわしい。 これには二つの理由があげられそうだ。一つは日蓮宗との関係だ。清正が深く日蓮宗に帰依していたことは事実で、 信者というよりも行者といった方が適切かもしれない。従ってその布教にも大きな力となった。 清正逝去後、日蓮宗の寺院では清正を模範的な信徒として、また布教の功労者としてたたえたのが、 いつの間にか清正自身を信仰の対象にしてしまった。“清正公様”がそれで、主として全国の日蓮宗寺院の中に、 或いは独立して堂が建立されている。ここまではいいのだが、これが庶民の人気や寺の商法がからみ合って、 清正は豪傑のサンプルのようになってしまい、“清正公様”は武力願望の対象のようになってしまった。 戦争中などは、出征兵士が武運長久を祈り、今でも相撲の社会などでは信者が多いという。 もう一つは、講談、芝居などの影響であろう。清正は領民ばかりではなく、他藩の人々からも大変人気があった。 誠実で信義に厚かったので大名間の評判もよく、出処進退が明解で、気はやさしくて力持ちはいつの世でも庶民からしたわれる。 講談や芝居は、この人気を背景にし、大きく尾ひれをつけて喧伝する。 この二つがからみ合って、清正への庶民のイメージが生れ、固定した認識が定着してしまったといっていい。 これは清正巷談中の最大の誤謬で、この点清正は、再認識されていい数少ない戦国武将の一人であろう。 |
|
(文:片山丈士「清正巷談異聞」より) |
(C)2016 身似明星