

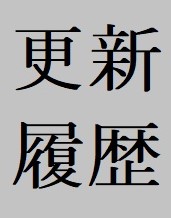
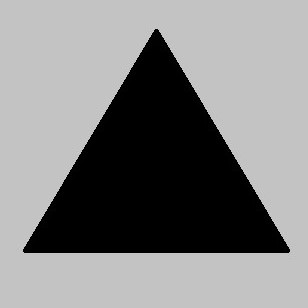

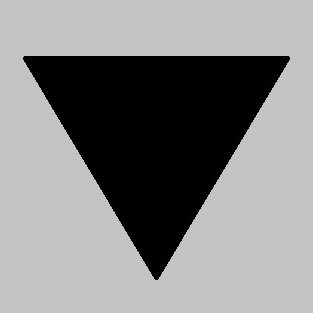

↑
| 清浄院 家康の従兄妹 |
|||||||||
| 本覚院 菊池武宗の娘 | 清正 | 正応院 玉目丹波守の娘 | |||||||
| 忠正 | 古屋 | あま | 忠広 | ||||||
| 九歳で早世 | 榊原家、後に 阿部家に嫁す |
紀伊家初代 頼宣夫人 | 寛永九年改易 庄内丸岡へ | ||||||
| 清正の室と子 | |||||||||
|
清正の糟糠の妻は正応院といった。正応院というのはもちろん戒名であるが、生前の名がわからぬのでそのまま使用する。 正応院は、肥後南郷の住人、初代玉目丹波守の娘だ。正室といっても差し支えあるまい。正応院には男女二人の子供があった。 兄は清正の遺領を相続した忠広で、妹は紀伊頼宣に嫁したあま姫である。 |
| 清正 | 正応院 玉目丹波守の娘 |
|||||||||
| あま | 忠広 | |||||||||
| 紀伊家初代 頼宣夫人 |
寛永九年改易 庄内丸岡へ | |||||||||
| 正応院の子 | ||||||||||
|
忠広は慶長五年の生まれで、幼名を虎之助(または虎藤)といった。慶長十五年から清正逝去までの間、質として江戸にいた。
十一歳で父の封を継ぎ、慶長十八年に従五位下肥後守、元和六年には従四位下侍従に任ぜられ、将軍秀忠の一字を貰って忠広と改名した。
同十九年、故蒲生飛騨守秀行の娘が秀忠の養女として忠広に入輿している。この女は、家康の三女振姫(秀行の妻)の長女だから、
家康の孫であり、秀忠の姪に当たる。蒲生秀行は氏郷の嫡男である。
忠広は寛永九年、三十三歳の時、幕府の弾圧によって出羽庄内に配流され、肥後は細川越中守の領地となった。
忠広は庄内鶴岡城主酒井宮内大輔忠勝に預けられ、一万石を与えられていたが、承応二年、配所で逝去した。享年五十四、
戒名は帝光院殿覚日源大居士である。忠広は、配流になるまでよく父清正の後を守ったようだ。 あまは、慶長六年の生まれで、同八年には清正と家康との間で家康の愛児長福丸(のちの頼宣)との婚姻が約された。同十五年、家康が、 三浦長門守為春を肥後に派遣し、結納を取り交わした。正式に頼宣の北の方として入輿したのは、清正逝去後の元和三年である。 あまの輿入れの際、持参した調度物品は善美を尽くしたもので、加藤家の宝物といわれるものも多かった。 いわゆる御三家の一である紀伊家の始祖大納言頼宣は、家康の秘蔵っ子であり、幼少から並々ならぬ才能をあらわしていた。 頼宣ははじめ常陸国水戸城を与えられ、常陸介頼将といった。その後、駿河遠江国五十万石に転じ(あまの入輿はこの時である)、 元和五年には、紀伊ならびに伊勢の内を併せて五十五万五千石の領主となったのだ。後年頼宣が、家康の期待どおり、 徳川第一の人物と称されるようになったのは多言を要しない。家康が、清正にあまを貰う約束をしたのは、慶長八年十月だから、 頼宣はまだ生後まる一年半だ(頼宣は慶長七年三月七日生)。まことに気の早い話だが、 ここにも家康の清正へのなみなみならぬ配慮が覗われる。ちなみに紀伊二代の光貞はあまの出生であり、 八代将軍吉宗は光貞の三男であるから、あまにとっては紛れもない孫である。その後、家重、家治、家斉、家慶、家定、 家茂といずれも紀伊家の血筋が将軍になっている。あまが幕府の手によって葬られた加藤家の息女であることを思うと、 まことに奇すしき因縁といえよう。あまと頼宣ははいわゆる琴瑟相和し、忠広に幕府の黒い手がのびたおりも、 頼宣は忠広救出に奔走している。あまは寛文六年、六十六歳で亡くなっている。戒名は瑤林院殿秀日芳大姉である。 熱心な日蓮宗の信者であった。 正応院は、忠広とともに雪深い庄内に下り、慶安四年に死去している。法号は正応院殿日怡大徳尊である。墓は鶴岡市本住寺に、 忠広と並んで建てられている。 清浄院は、家康の伯父の水野泉州(和泉守)忠重の娘で、家康は従兄妹であるこの女を養女として育て、清正に入輿させた。 慶長四年、秀吉が亡くなってからのことで、清正はすでに四十歳近くになっていたわけだ。いわば押しつけ女房のようなもので、 家康一流の懐柔策であることはいうまでもない。その後家康は、清正に対して何かにつけ“内縁の間であるから”という言葉を使っている。 徳川家公認の奥方、或いは徳川時代の公儀の奥方というところであろう。幕府関係の文書には、 この清浄院が正室になっているのは仕方ないとしても、忠広の生母として扱っているのには恐れ入る。 清正はこの奥方によほど警戒心を持っていたらしく、部屋へ入るときも刀を離さなかったという。 関ケ原大戦のおり、三成一派は、諸大名が家康に同心するのを防ぐため、在阪の夫人を人質にする計を立て、 これに抗した細川忠興夫人ガラシャお玉の方は、壮烈な自尽を遂げた。そのおり、この清浄院は大阪邸にいた。 清正は熊本でそのことを知り、清浄院を大阪から脱出させたのだが、これがなかなかふるっている。 脱出行の立役者は、朝鮮の役の総船奉行をつとめた梶原助兵衛景俊と、後年清正に殉死した大木土佐守兼能である。 両名は密議を凝らし、まず景俊が病人に扮し、駕籠で医師通いを始めた。景俊は、大綿帽子をかぶり、大夜着を後にかけ、 乗物の左右の戸を開いて往復した。邸外には番所がいたるところにできていて、最初のうちは内部をくわしく調べたが、 日が経つにつれて、「ああ、いつもの病人か」と黙って通すようになった。 二十日余りたって、もう大丈夫と睨んだ景俊は、清浄院を大夜着の中に隠して後に押しつけ、 大綿帽子をかむって身を駕籠一杯に横たえて邸を出た。大木土佐は、病が重くなったと称して、駕籠側につき添って歩いた。 もし乗物を調べられたら、番兵と一戦を交え、遁れられなくなったら清浄院を刺して自決する手筈だったという。 しかし番所では、毎日のことなので格別のこともなく、無事、兼ねて用意の舟まで辿り着くことができた。 舟には満水した水溜桶が三つ据えてあり、その中の一つが中底になっていた。その中底の下に、清浄院を押し込んだのだ。 港口には船番所があり、船内の検査があったが、上からみればいずれも満水した桶なので、仕かけに気がつかず、 無事脱出して熊本へ帰った。夜着の中に隠れたり、水溜の中底の下に押し込まれたり、清浄院もひどい目にあったわけだが、 これも義父家康のためと諦めたのだろう。細川ガラシャ夫人が自決したのは、清浄院退出後であるという。したがって、 もう少し後だったら、こうした苦労しなくともよかったかもしれない。 忠広配流後の消息は不明だが、墓所の本圀寺の過去帳によると、明暦二年に亡くなっている。清浄院忠日寿大姉である。子供はいなかった。 清正には本覚院という側室があった。側室などといえば、いかにも閨房が乱れているようだが、当時の常識では、 大名にたった一人しか側室がいなかったというようなことは、まことに珍しい部類に属する。本覚院は菊池武宗の娘で、 古屋姫と忠正の二人の子があった。古屋は慶長二年に生まれ、同十一年、上州館林城主榊原康政の嫡子康勝に嫁いだ。 榊原家が徳川譜代の名門であること、この縁組が家康の斡旋によることはいうまでもない。 ところが、康勝が早世し、子がなかったので、のち阿部修理亮正澄に再嫁した。正澄は大阪城代備中守正次の嫡子である。 古屋は寛永四年、三十歳で亡くなった。戒名は本浄院殿妙智日昌大姉である。 |
| 本覚院 菊池武宗の娘 | 清正 |
|||||||||
| 忠正 | 古屋 | |||||||||
| 九歳で早世 | 榊原家、後に 阿部家に嫁す | |||||||||
| 本覚院の子 | ||||||||||
| 古屋の弟は慶長四年に生まれ、幼名を熊之助と称し、のち将軍秀忠から一字を貰って忠正と改名した。忠正は江戸で質となっていたが、 慶長十二年正月二十七日病死した。九歳であった。戒名は理性院殿宗覚日等居士である。忠正はなかなか才気があり、 秀忠からも可愛がられ、病中、半井蘆庵という名医を秀忠から度々見舞いに派遣されたという。忠正の墓は、 熊本から大分離れた八代の宮地にあるのだが、これは清正が見た夢によるものという。愛児の死を哀しんでいた清正は、 ある夜忠正が、「ここは北に向かって流れる谷川を上った所だ」といいながら遊んでいる夢を見、覚めてから地図を開いて、 そこが宮地であることをたしかめたのだという。清正は忠正の菩提寺として、墓所に本成寺(のちの宗覚寺)を建立している。 古屋、忠正の母である本覚院の墓は、本覚寺にある。 |
|
(文:片山丈士「加藤清正 下巻」より) |
(C)2016 身似明星