

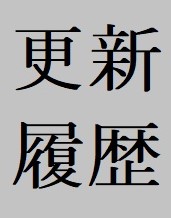
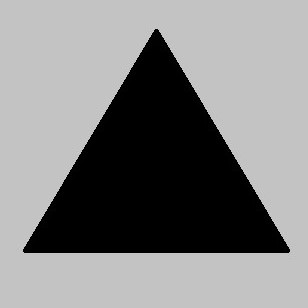

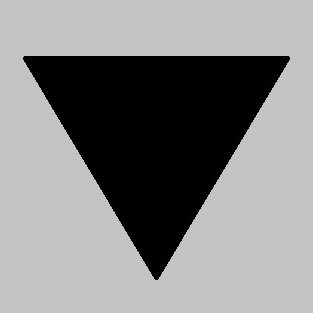

↑

熊本城 清正像 (熊本城HPより) |
|
関ケ原の役後から慶長十六年に逝去するまでの清正の晩年で、特筆すべきことが三つあります。
第一は、その卓抜な治政です。驚異的な水利土木事業を完成し、産業の開発に意を注ぎ、通商貿易にも深い関心を示しています。
他面、文化の開拓にも非常な熱意を持ち、仏書、経書、儒学等の研究、詩歌、文学の奨励、茶の湯、歌舞伎の普及につとめました。
日蓮宗に対する帰依は、年々その深さを加え、自身の信仰を深めると同時にその広布にも努力し、
社寺関係に対する尽力は枚挙にいとまがありません。第二は築城です。慶長六年から十二年までの七カ年の歳月を費やして、
当代の名城といわれた熊本城を竣工したのをはじめ、江戸城の増築、尾張名古屋の築城等にも当たっています。
清正のすぐれた築城技術は、内外に遺憾なく発揮されました。そして第三は、逝去直前に行われた世にいう二条城会見です。 治政、築城はまた別項で、二条城会見は毒殺説も含め“巷談異聞”の中で詳述していますので、ここでは清正の逝去の様子と、 晩年の苦悩についてまとめました。。 |
|
二条城会見を終えて帰国した清正は、巨木が根こそぎ倒れるように逝去しました。それはまことにあっけない、あわただしい最後でした。
清正は、海路肥後に帰ったのですが、船中で病を得、五月二十七日に熊本に着いた時は、すでに重体であったようです。
その後、約一ヶ月闘病を続けましたが、奇しくも誕生日の六月二十四日に永眠しました。享年五十でした。 |
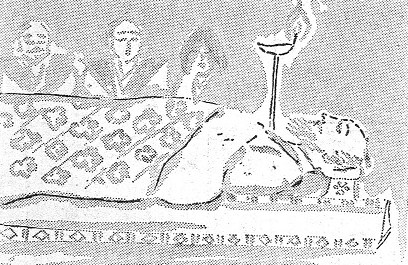
連載清正挿絵より:絵高橋裕一 |
|
いくつかの毒殺説についてはここでは省略するが、ともかく豊臣につながる大名が、三、四年の間にバタバタと亡くなったこと、 家康が大阪を攻めたのはその後であったこと、これらの大名は、幸長の三十八歳を最年少として、いずれも家康より若かったこと、 家康の策謀家的性格などから生れ出たものだろう。(巷談異聞の中で詳述) 六月十七日、清正の病状報告と万一の場合の子息虎之助(忠広の幼名)への家督相続を請願するため、和田備中と飯田角兵衛が江戸、駿府へ出発したのだが、 この時両名を派遣したのは、清正の意志ではなく、物も言えない主君に代わって、重臣たちが相談して取り決めたというから、 清正がともかく言語障害を起こしていたことは事実と思われる。したがって、遺言などもなかったというのが正しいようだ。 清正の遺言として伝えられる“吾死せば具足を着せ、太刀を佩かせて棺に入れるべし。末世の軍神たらん”というようなものは、 後年の作であろう。 清正は六月二十三日から危篤状態に陥ったようだ。家臣一同は城中に詰め、領民は声を呑み、ひたすら平癒を祈願したが、そのかいもなく、 翌二十四日の丑の刻(午前一時)に息を引きとった。肥後全国は哀悼に閉ざされたという。 清正逝去の翌朝、大木土佐守が自宅で切腹殉死した。清正は殉死を許さず、万一の時は家臣協力して幼い虎之助を護ってくれるよう望んでいたというが、 病状が前述のようなものなので、許すも許さぬもなかったであろう。大木土佐は、佐々成政(前肥後藩主)の家臣だったが、 成政亡き後は清正に招かれて仕え、人物を買われて三千石を与えられるようになった。清正を慕い、追腹を切ったわけだ。 またこの大木土佐は、関ケ原の際の清正夫人の大阪脱出の立役者でもある。 |

本妙寺 大木土佐守の墓 |
| 殉死者はもう一人出た。それは金官という朝鮮人である。清正は朝鮮から帰国する時、約三百人の鮮人を連れてきたのだが、 金官はその中の一人で、朝鮮後宮の財務を司る役をつとめていた。前役で、二王子とともに捕らえられ、のち清正を慕って近習に加わり、 二百石を貰っていた。清正逝去の二十四日に切腹しようとしたのだが、二人の子供に見つけられ、脇差を取上げられてしまった。 以降厳しく監視されていたのだが、半月後、家に来た桶屋が古桶の輪を替えている間に、その鉈をとって腹十文字に掻き切って死んだという。 (金官については“清正と鮮人”で詳述します。) |

本妙寺 金官の墓 |
|
幕府は、虎之助に家督相続を許したが、主なる家臣二十人の人質をとって江戸に置いた。虎之助は、この時わずかに十歳で、
質として江戸にいたために父の死に会えなかった。 清正の本葬は、虎之助帰国後の十月十三日、日蓮宗京都大本山本圀寺貫主日桓上人の引導によって行われ、 飽田群中尾山(現在の本妙寺浄池廟)に葬られた。法号は、浄池院殿永運日乗大居士である。殉死した大木土佐守と金官の棺も、 同じ日桓上人の引導で清正の廟の左右に葬られた。清正の廟所は、飯田角兵衛と三宅角左衛門が普請奉行となって築かれたものだが、 清正の遺骸は鎧冑の武装のまま石棺に朱詰めにし、地下五十尺のところに埋葬されたという。その地点は、 現在本妙寺廟所内に安置された清正の木像の真下に当たるということだ。 (清正の墓は実は庄内にもあります。これについては“清正廟論争”で詳述します。) |

本妙寺 浄池廟 |
|
(文:片山丈士「加藤清正 下巻」より) |
|
天は清正に長寿を与えなかった。今日からみれば、四十から五十までの十年間は、人生における最も充実した時期といえるのだが、 清正にはそれが晩年になってしまった。しかし今日と同じように、清正にとってもその晩年は、まことに充実した意義ある期間であった。 それは、すぐれた治政者としての面を遺憾なく発揮できたからだ。もし、落ちついて治政に専念できたこの期間がなかったならば、 清正は単に勇将として記憶されるにとどまるであろう。 清正は、あたかも天寿を予期したように、異常な情熱を領民の福祉に傾けたのだが、その業績とは逆に、 清正個人としては苦悩に充ちた晩年であった。江戸城修築の石材運搬を課せられた清正が、派手な格好でお祭りのようにして運んだり、 着流しで馬に乗り、江戸城下を徘徊したり、こうした派手な奇矯な振舞いは、年とともに数多く見られるようになった。 たとえば、慶長十五年の名古屋築城のおりに彼の地で展開した行動などは、その最たるものといえよう。 |

名古屋城と清正像 |
|
清正が名古屋に滞在したのは、同年二月から八月末までの約半年であるが、その間の派手さ加減は、中京の人々を驚かせ、
長く語り草にされたのだ。清正は石垣工事を一手に引き受けたのだが、熱田から巨大な角石を運ぶ際、石を毛氈で包み、
その上を青い大綱でからげ、石の上には片鎌槍を立て、粧を凝らした小姓とともに、
みずからも江戸でのような派手な衣装を着けて石の上に乗り、大音声できやりを謡いながら、
華麗ないでたちの家臣たちに本綱を曳かせたという。さらに清正は、沿道に一杯集まる酒、肴、餅、
菓子等の立売から残らず品物を買い上げて、群集に与えたので、商人も見物人も皆その綱に取つき、喜び浮かれながら曳いて行ったという。 清正は滞在中、現今の桜天神の辺に膨大な屋敷を持っていた万松寺の中に、宿舎を新築して住んでいたのだが、肥後から連れて来たり、 現地で集めたりした役者や芸達者な小姓、女たちと夜な夜なさんざめき、他の諸侯に目を見張らせたという。 清正陣中のこうした豪奢絢爛たる振舞いが、名古屋の話題になり、 &emsp:及びなけれど万松寺の花を、折って一枝ほしゅうござる。 という俗謡まで生まれた。 清正が、なぜそんな衆目を驚かすような派手なことをやったかについては、いろいろの説がある。 名古屋は故郷の地だから、心から愉快でならなかったろうというような単純なもの、または工事を進捗させる手段であったとか、 或いは家康の監視の目をごまかすためであるとかである。もちろんそういうこともあったかもしれないし、また、 家康の外様大名政策に対するレジスタンスということもあるかもしれない。金を搾り取ろうとする家康の前で、 金なんか何ぼでもくれてやるとばかり、湯水のように使ったのかもしれない。一つの自虐的抵抗だ。しかし、こうした現象は、 名古屋においてだけではないのだ。江戸でのことは前に書いたが、領国肥後でも、 よそ目には奢侈逸楽にうつつを抜かしているとしか思われないような行動がしばしば見られた。 清正は年をとるにつれて酒に親しみ、風流を愛するようになった。古文書や文献などをよく読んでみると、 清正の様子はただごとではないものがある。端正素朴なこれまでの清正とは人が変わったように思えるのだ。しかし、人が変わったのでも、 乱心したのでもないことは、二条城会見の際の態度や、物に憑かれたように治政に献身した反面を見てもよくわかる。 「肥後殿は苦しいのだ」 清正のそうした姿に、筑前の黒田はこう呟いたというが、清正はまさしく苦悩していたのだ。 豊臣や加藤の将来、抜きがたい勢力となってしまった家康、もはや取り返しのつかない過去への悔恨が、 年とともに直情律儀な清正の骨を噛んでいたともいえよう。奢侈逸楽に耽っている清正は、 実は内的苦悩に喘いでいたことを知って貰いたいのだ。 清正は、家康が秀頼にどのような考えを持っているかということも、口ではどのようなことを言っても、 豊臣派の巨頭として己の身辺を見張っていることも、よくわかっていたに違いない。そしてまた、 度しがたい世間知らずな淀君の存在も・・・。 もう家康にしてやられる清正ではなかった。恐らく清正には、豊臣や己の将来が見通せたことであろう。そうした不安と、 家康を強大にしてしまった己への反省が、四六時中彼の脳裏を去来し、苦悩は年とともに深くなっていったのではないか。 福島正則をたしなめた清正の言葉を書こう。 「それなら国に帰って合戦するがいい。もしそれがいやなら黙って命令に服すべきだ」 この言葉の中に、どうにもならない清正の苦悶がよくあらわれているではないか。 |

八景木谷公園の清正像 (熊本城HPより) |
| その偉大な治政は、肥後百年の計を樹立したものと言っても過言ではないのだが、 それが清正の苦悩の日々に成し遂げられたことを想うと、感ひとしおのものがある。清正の晩年は、 清正自身にとっては苦悩に充ちたものであっても、領民とその子々孫々にとっては、誠に輝かしい仕合わせな期間であったのだ。 領民の仕合わせは、清正の苦悩がもたらしたものとは言わないが、己の苦悩に周囲をひきずり込むことなく、 逆に苦悩を噛みしめながら、周囲の仕合わせの為に献身した清正には頭の下がる思いだ。 |
|
(文:片山丈士「加藤清正 下巻」より) |
(C)2016 身似明星